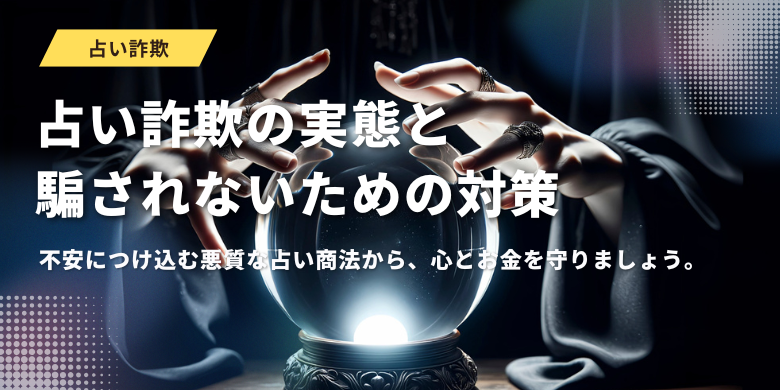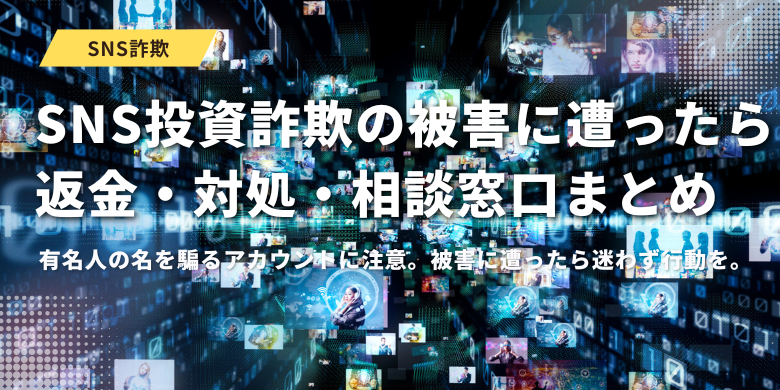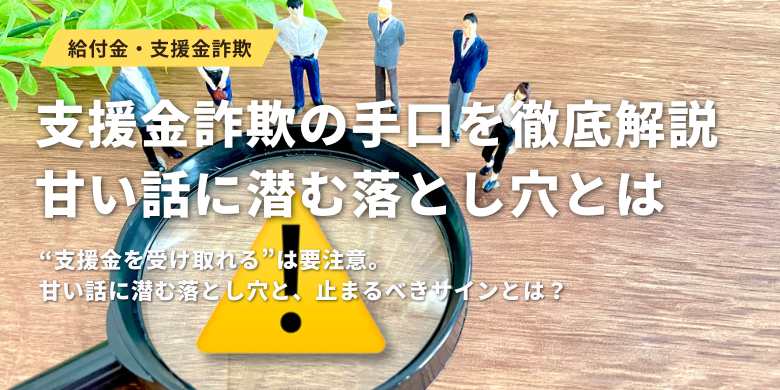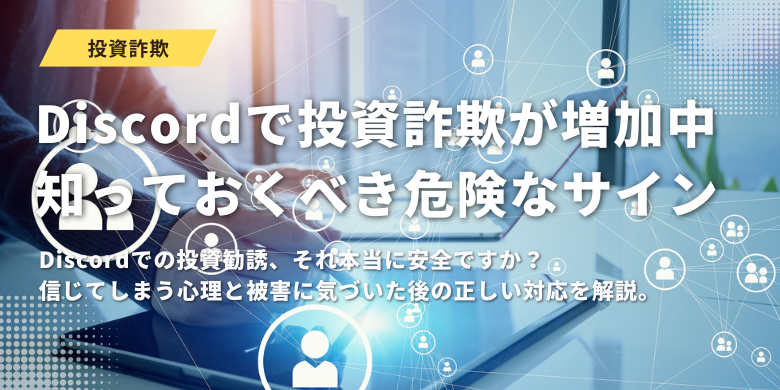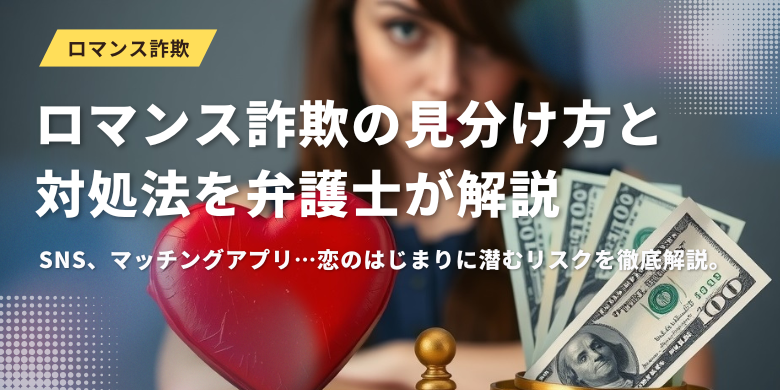【実例あり】仮想通貨詐欺の最新手口を弁護士が解説

近年、暗号資産(仮想通貨)市場の拡大に伴い、関連する詐欺被害が急増しています。
「高い収益率を保証する」「必ず儲かる投資話」といった甘い言葉で投資家を誘い、資産を騙し取る悪質な手口が後を絶ちません。
SNSやマッチングアプリを通じた巧妙な勧誘、偽の取引所サイト、実態のないICO案件など、詐欺師の手口はますます巧妙化しているのが現状です。
本記事では、仮想通貨詐欺の代表的な手口から実際の被害事例、そして被害に遭った際の具体的な対応方法まで詳しく解説します。
大切な資産を守るための知識として、ぜひ最後までご覧ください。
仮想通貨詐欺とは
仮想通貨詐欺とは、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産を悪用し、投資家から金銭や資産をだまし取る犯罪行為です。
近年の詐欺は、仮想通貨の金融商品としての複雑性や匿名性を利用し、従来の投資詐欺同様、被害者に誤った情報を与えて資金を詐取する手口が注目されています。
詐欺師は「仮想通貨なら短期間で大きな利益が得られる」「今だけの特別な投資機会」といった誘い文句で投資家の関心を引き、最終的には投資資金を持ち逃げします。
被害者の多くは仮想通貨に関する知識が不足しているため、詐欺であることに気づくのが遅れがちです。
仮想通貨詐欺の特徴
仮想通貨詐欺は、主に以下のような特徴を持つ犯罪行為として定義されます。
詐欺の基本構造
- 実在しない仮想通貨プロジェクトへの投資勧誘(例:ICO詐欺)
- 正規の取引所やウェブサイトを装った偽サイトや偽アプリによる資産搾取
- 「高配当」「元本保証」など現実的ではない条件で投資を煽る
- 著名人の名前を無断で使用して信頼性を偽装する
標的となりやすい層
仮想通貨詐欺の被害者は幅広い年齢層に及びますが、特に以下のような方が狙われやすい傾向があります。
- 仮想通貨投資の初心者
- 高齢者(デジタル技術への理解が不足している場合)
- 副業や投資で収入を増やしたいと考えている会社員
- SNSを頻繁に利用している若年層
日本国内の被害状況
国民生活センターや金融庁の統計によると、暗号資産の相談・トラブルはここ数年で急増しています。2023年度のSNS型投資詐欺は被害件数2,271件、被害総額約278億円となり、SNSを含む非対面型投資詐欺が目立ちます。
被害者は30代から60代が中心ですが、幅広い年代で確認され、勧誘手法ではSNS等のネット上での声かけが主流となっています(件数の6割以上とも報告)。
令和5年中のSNS型投資・ロマンス詐欺の被害発生状況等について|警察庁Webサイト
被害額
平均200万~500万円前後との相談もありますが、1,000万円超や数千万円規模の事例も発生しています。
勧誘手法
SNSを通じた投資グループメッセージや、マッチングアプリで知り合った相手からの勧誘による詐欺が増加。
特に近年は、マッチングアプリや婚活サイトを利用した「ロマンス詐欺」タイプの手口が急増しています。恋愛感情や親密な関係を装って信頼を得た後に仮想通貨投資を勧め、最終的に資金を騙し取る手法が多数報告されています。
被害者は連絡が途絶えた時点で詐欺と気づくことが多く、多額の損害が生じています。
詐欺師が狙うターゲット層の特徴
仮想通貨詐欺の加害者は、被害者を選ぶ際に以下のような特徴を持つ人を意図的にターゲットにします。
心理的な脆弱性を持つ人
- 経済的な不安を抱えている
- 老後資金への不安が強い
- 現在の収入に不満を持っている
- 投資で一発逆転を狙いたいと考えている
情報収集能力の特徴
- インターネットの情報を鵜呑みにしやすい
- 専門用語への理解が曖昧
- 第三者への相談をあまりしない傾向がある
- 急いで判断する癖がある
社会的な立場
- 家族や友人に投資のことを相談しにくい環境にいる
- 退職後で時間に余裕がある
- 在宅ワークなどでSNSを見る時間が長い
詐欺師はこうした特徴を巧みに見抜き、ターゲットに応じた勧誘手法を使い分けています。
自分がターゲットになりやすい特徴に当てはまる場合は、特に注意深く投資話を検討する必要があります。
仮想通貨詐欺の手口5選
仮想通貨詐欺の手口は日々進化しており、従来の投資詐欺にデジタル技術を組み合わせた巧妙な方法が次々と生まれています。
詐欺師たちは被害者の心理を巧みに操り、信頼関係を築いてから大金を騙し取る手法を用います。
①SNSでの個別勧誘
Instagram、X、LINEなどのSNSを通じて個人的にアプローチし、仮想通貨投資を勧誘する手口です。
特に美男美女のプロフィール写真を使用し、恋愛感情を絡めた「ロマンス詐欺」の要素を含むケースが急増しています。
典型的な詐欺の流れ
- SNSで投資に成功したかのような投稿を継続
- 相手から関心を示されたら個別メッセージを送信
- 日常会話から始めて信頼関係を構築
- 投資の成功体験を語り、相手の興味を引く
- 「特別にあなただけに教える」として投資を勧誘
詐欺師は数週間から数ヶ月かけて被害者との関係性を築き、「あなたのことを思って教えている」という印象を与えます。
被害者が投資を躊躇すると、「チャンスを逃すと後悔する」「私を信じてくれないのか」といった心理的圧迫を加えることもあります。
②偽のWEBサイト(詐欺サイト)による誘導
仮想通貨詐欺で頻出するのが、正規の取引所や金融機関を装った偽サイトへの誘導です。
見た目は本物そっくりに作られており、初見では見分けがつかないほど精巧です。
典型的な詐欺の流れ
- SNSやメールで「稼げる投資サイト」などのリンクを送付
- リンク先のWEBサイトでアカウント作成・入金を促す
- 入金後、ダッシュボード上では増益しているように見せる
- 出金を試みると「税金」「手数料」の名目で追加送金を要求
- 最終的にサイトが閉鎖、連絡が取れなくなる
詐欺サイトのURLは一見正規サイトに似せてありますが、ドメインが異なる、SSL証明書がないなどの特徴があります。Google検索ではなく直接送られてきたリンクには注意が必要です。
③偽のアプリによる資金詐取
スマートフォンのアプリストアを悪用した、偽の仮想通貨取引アプリによる詐欺も急増しています。
正規のサービスを装ったアプリが、資金の預け入れや個人情報の収集を目的としています。
典型的な詐欺の流れ
- SNSやLINEでアプリのダウンロードを案内
- 非公式のリンクやAPKファイルでアプリをインストールさせる
- アプリ内で「ボーナス付与」などを訴求し、入金を誘導
- 入金後、アプリが動作しなくなる or 出金ができない
- 詐欺業者と連絡が取れなくなる
特にAndroid端末では、Google Playを経由しないインストール(野良アプリ)による被害が目立ちます。非公式アプリの使用は絶対に避けましょう。
④フィッシング詐欺による情報窃取
仮想通貨の管理に必要なウォレットの秘密鍵やパスフレーズを盗む目的で、フィッシング詐欺が横行しています。正規のサービスを装ってログイン情報を入力させる手口です。
典型的な詐欺の流れ
- 取引所やウォレットサービスを騙ったメールやSMSを送信
- 「セキュリティ確認」や「異常ログイン通知」などで不安を煽る
- 偽のログインページに誘導し、ID・パスワードを入力させる
- 盗まれた情報で資産が勝手に送金される
- 被害者が気づいたときには資産は既に移動済み
仮想通貨の送金は基本的に取り消しができないため、一度盗まれた資産の回復は非常に困難です。不審な通知やリンクは、必ず公式サイトで確認しましょう。
⑤ICOやNFTを装った新型詐欺
仮想通貨の中でも比較的新しい概念であるICO(イニシャル・コイン・オファリング)やNFT(非代替性トークン)を悪用した詐欺が近年急増しています。
これらは本来、革新的な技術・アート・資産価値を持つプロジェクトですが、技術的な複雑さや市場の未成熟さを逆手にとって、知識の浅い投資者を狙う手口が蔓延しています。
これらの詐欺は、見た目は先進的なプロジェクトであるかのように装いながら、実際には中身のない虚偽のプロジェクトであることが大半です。
典型的な詐欺の流れ
- SNSや広告で新しい仮想通貨・NFTプロジェクトを宣伝
- 著名人・専門家の偽推薦やメディア掲載を装って信頼を獲得
- 「限定販売」「初回購入特典」などの希少性を強調して入金を促す
- 投資後、ダッシュボードやアプリ上で利益が出ているように見せかける
- 出金を試みると口実をつけて拒否、最終的に連絡が途絶える
実際にあった仮想通貨詐欺の被害事例
仮想通貨詐欺の被害に遭っても、適切な対応を取ることで返金に成功するケースがあります。
重要なのは被害に気づいた瞬間から迅速に行動し、証拠を保全しながら専門家に相談することです。
以下では、実際にあった仮想通貨詐欺の被害事例をご紹介します。
事例①:SNS経由での「月利保証」詐欺で被害額320万円
投資系SNSを通じて知り合った相手から、「月利15%保証」「元本保証」といった内容の投資話を持ちかけられました。
被害者は高利回りの言葉に魅力を感じ、やり取りを重ねるうちに信頼感を深めてしまいます。
その後、指定された口座に仮想通貨を通じて合計320万円を送金。最初のうちは配当として少額の振込があり、安心して追加の資金も送ってしまいました。
しかし、出金を依頼したタイミングで相手との連絡が突然取れなくなり、SNSのアカウントも削除されていることが判明。ようやく詐欺被害に遭っていることに気付きました。
事例②:偽ICO案件で350万円の被害
新規仮想通貨プロジェクトへの投資を募る偽ICO案件による被害事例です。
被害者は「革新的なブロックチェーン技術を開発中」とうたうプロジェクトを信じ、合計350万円を出資しました。
公式サイトやホワイトペーパーは精巧に作られており、有名企業との提携情報や著名人の推薦コメントも掲載されていました。しかし、投資から数ヶ月後、プロジェクトの公式サイトが突然閉鎖。運営者との連絡も取れなくなり、掲載されていた情報がすべて虚偽であったことが判明しました。
よくある質問(Q&A)
仮想通貨詐欺に関して寄せられるよくある質問にお答えします。
被害に遭った方や詐欺かどうか判断に迷っている方の参考になれば幸いです。
Q.仮想通貨の送金は自己責任と言われますが、返金できるの?
A.ケースによっては可能です。相手の詐欺行為を立証できれば、法的に返金請求ができます。
仮想通貨の送金は確かに不可逆的な取引ですが、詐欺による送金の場合は民法上の不法行為として損害賠償請求が可能です。重要なのは詐欺であることを証明できる証拠を保全することです。送金履歴、相手とのやり取り、勧誘内容などの記録をしっかり残し、適切な法的手続きを踏むことが重要です。
Q.仮想通貨取引アプリで出金できなくなりました。これは詐欺ですか?
A.「アプリに残高があるのに出金できない」「出金するには“税金”や“手数料”が必要と言われた」などの状況は、典型的な詐欺の兆候です。
特に、Google PlayやApp Storeを通さず配布されたアプリや、運営元が不明なものは要注意です。
操作履歴やアプリ画面のスクリーンショットなどを保存しておくことをおすすめします。
Q.仮想通貨詐欺かどうか判断がつかないのですが…。
A.やり取りの内容や投資内容を確認することで、詐欺かどうか専門家が判断できます。
まずはご相談ください。
「絶対に儲かる」「元本保証」などの断言や、金融庁への登録がない事業者、運営者情報が不明確な案件は詐欺の可能性が高いです。少しでも不安に感じたら、投資を実行する前に専門家に相談し、第三者の客観的な視点で判断してもらうことが大切です。
Q.弁護士費用は高額ですか?
A.当事務所では、LINEによる初回相談を無料で受け付けております。
その後、具体的な対応をご希望の場合は、状況に応じてお見積もりを提示いたします。
費用面が不安な方も、まずはお気軽にご相談ください。
ご依頼前にご納得いただけるよう丁寧にご説明いたします。
まとめ
仮想通貨詐欺は年々手口が巧妙化し、一般の投資家や初心者が被害に遭うケースが増加しています。
SNSやマッチングアプリを通じた勧誘、元本保証を謳う偽プロジェクト、海外取引所を悪用した出金詐欺など、様々な手口で投資家を狙う悪質な詐欺師が後を絶ちません。
しかし、適切な知識と対策を身につけることで、こうした詐欺被害を未然に防ぐことができます。
万が一詐欺被害に遭ってしまった場合でも、迅速な対応により返金の可能性があります。
被害に気づいた瞬間から証拠を保全し、詐欺師とのやり取りや送金履歴を記録として残すことが重要です。また、一人で解決しようとせず、早期に弁護士などの専門家に相談することで、法的手続きを通じた効果的な被害回復が期待できます。
田中保彦法律事務所では、仮想通貨詐欺に強い弁護士が被害者の立場に立って返金対応をサポートしています。
大切な資産を取り戻すため、そして二次被害を防ぐためにも、少しでも詐欺の疑いがある場合はお気軽にご相談ください。